 新着情報
新着情報
令和7年1月21日「CKD医療連携を考える会」を開催しました。
~様々な連携と腎臓病療養指導士の活動を考える~
「CKD医療連携を考える会」が2025年1月21日、京都市下京区のホテル日航プリンセス京都において、対面形式で開催されました。
(康生会武田病院、田辺三菱製薬㈱:共催)
当日は多くの参加者が集まり、会場は満席となりました。

開会にあたり京都駅前武田透析クリニックの吉岡徹朗所長は、「この会は名称の通り、CKDと末期腎不全の病診連携を考えることを主旨としています。
近年、腎臓内科・透析領域ではCKD診療・啓発に始まり、HIF-PH阻害薬の登場やSGLT-2阻害薬がCKDにも適応拡大されるなど新たな展開があり、また末期腎不全の診療に関しても保存的腎臓療法の新たな方向性が開花しつつあります」と動向を語り、本日の演目を紹介。台風の影響で本会が延期となっていた経緯にも触れ、「本日の講演を大変、楽しみにしておりました。それでは皆様、どうぞ宜しくお願い致します」と朗らかに宣言しました。

第一部は康生会武田病院からの2演題です。
やすだ医院の安田雄司院長が座長を務め、康生会武田病院透析センターの川上享弘センター長が、「武田病院の透析医療について ~内シャント作成から外来透析まで~」と題し講演しました。
川上享弘センター長は、 腎不全専門医に紹介する適切なタイミング、そしてバスキュラーアクセス(以下、VA)を作成するタイミングについて紹介し、「当院ではガイドラインをもとに、『手術先行』の場合は保存期にVAを作成します。
1泊2日での局所麻酔の手術で、透析導入時の入院期間を短縮できるメリットがあります。これに対し『透析先行』は、尿毒症で救急搬送された場合やうっ血性心不全など、透析治療を行わないといけないケースで、後でVAを作成します」とし、自己血管を用いたAVF、人工血管を用いるAVG、そして長期留置型カテーテルなどVAの種類を丁寧に説明しました。
続いて川上センター長は、透析開始後の課題として「皆さん共通の悩みの種となるのがVAの狭窄や閉塞です。第一選択となるのはシャントPTA(経皮的バルーン拡張術)です」とし、動画を交えながら狭窄部の拡張やステント留置などについて説明しました。「当センターは医師4人体制ですので様々な対応が可能です。このほか、『穿刺した穴から膿が出る』、『血管に瘤ができて大きくなってきた』、『内シャントが心負荷になっている』など様々なシャントトラブルに対応しています」とし、看護師、管理栄養士、臨床工学技士などが連携するチーム医療を強調しました。
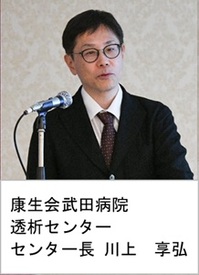
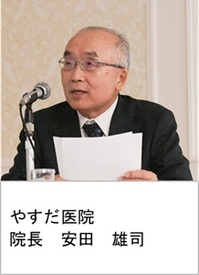
続いて同院透析センターの乾恵美部長が、「当院での透析時リハビリテーションの取り組み」と題して講演しました。
乾部長は、腎臓リハビリテーションの概要を説明し、「これまで安静のイメージがついていた腎臓病患者さんに、運動療法の必要性が注目されている」と、その効果とエビデンスについて説明。その一方で、透析患者さんが運動の時間を確保することの難しさを指摘しながら、その解決に向けた透析時運動療法ならびに令和4年の診療報酬改定で新設された透析時運動指導等加算について紹介しました。
そして、当院透析室で取り組んでいる透析時リハビリテーションについて説明。「当院の取り組みとして、患者さんのモチベーションを保ち運動療法の効果をあげるため、一番困っていること、夢をお聞きしています。」と、11人の患者さんの例を紹介。「『堀川通りの横断歩道を1回で渡り切れるようになりたい』、『こけないようになりたい』など、切実な希望をお持ちです。限定的な期間・症例数ではありますが、成果が現れてくる方はより具体的な希望をお持ちです。それだけその事に困っておられ、リハビリを頑張ってくださるのです。」と、目標を具体化することの重要性とその努力に対して賛辞を送ることの大切さを強調しました。乾部長は、「夢を語ろう」のキャッチフレーズで講演を終えました。
質疑応答で、乾部長は80代女性の透析患者さんの例を挙げ、「何歳だから透析導入や運動療法を見合わせるというのではなく、個々の患者さんとの向き合いを大切に考える自身の医療へのスタンスを表現するものとして、地域連携の会で発表させていただいた」、で締めました。

特別講演では、熊本大学大学院生命科学研究部腎臓内科学の桒原孝成准教授が登壇されました。「CKD診療連携体制の構築、そして発展を目指した取組みと課題 ~病診連携におけるSGLT-2阻害薬の使い方も含めて~」と題し講演を行いました。
座長の武田純院長は冒頭、「CKDについては当初より、病態、診断と治療、生活習慣の改善指導など全く異なるものがごちゃまぜの概念であり、患者さんのメリットになるのだろうかとの疑問を持っていました。この領域での地域連携、診療科同士の連携を行うなか、難しさを感じたことから、課題を焙りだすような研究会になればと、本会を起ち上げました」と設立時を振り返りました。そして、「この講演が、課題の多いこのCKDの連携において、一つの大きな示唆を与えて頂けるのではないかと思っています」とし、講師を紹介しました。

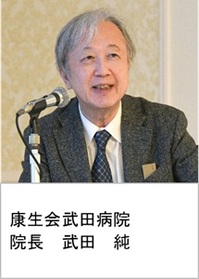
桒原准教授は、熊本市のCKD対策が全国に先駆け2009年に開始されたこと、当初は新規透析導入者の割合が全国平均の1.47倍あったものが、現在では1.03倍となっていることなどの成果を示し、「一番の核となりますのは『2人主治医制』『病診連携登録医制度』です。こうした連携には医師以外の職種がいないことには成り立ちません」とし、対策の維持・発展にあたり「地域の企業(保険者)はもとより、行政(熊本市)が入ってくれているのが重要」と、連携体制を説明されました。
さらに大きなポイントとして桒原准教授は、コメディカルの中心となる腎臓病療養指導士(以下、指導士)について取り上げ、「これは2018年に始まった制度で、異動等で更新されないままになるなど当初は様々な課題点がありました。そこで独自に指導士の活動の場を設けようと、『熊本県腎臓病療養指導士連絡協議会』を全国に先駆け2019年に立ち上げました。現在では、生涯学習支援事務所に業務を委託し、同協議会が支援するなど、産官学による連携体制を構築し、エビデンス構築に向けた活動とCKDの啓発活動を続けています」と語りました。
さらに桒原准教授は、「参加した腎臓病療養指導士の皆さんからは、『病院での業務は勿論、一般の方への啓発のお役に立てて良かった』など喜びの声が多く、今では指導士の参加数に上限を設けているぐらいです」と笑顔で説明しました。
質疑応答では、会場から次々と質問が寄せられ、桒原准教授は一つひとつ丁寧に回答されました。なかでも、腎臓内科の専門医が地域で不足していることや、指導士への期待について話題が集中しました。桒原准教授は、「プラクティカルに対応するため、CKDやDKDにまとめてしまっていますが、そこには嚢胞腎など様々な疾患があります。熊本では、指導士をはじめコメディカルの方々が知識を持ちつつ、少しずつ個別対応ができるようになってきている段階です」と、徐々に体制を強化している状況を話されました。
